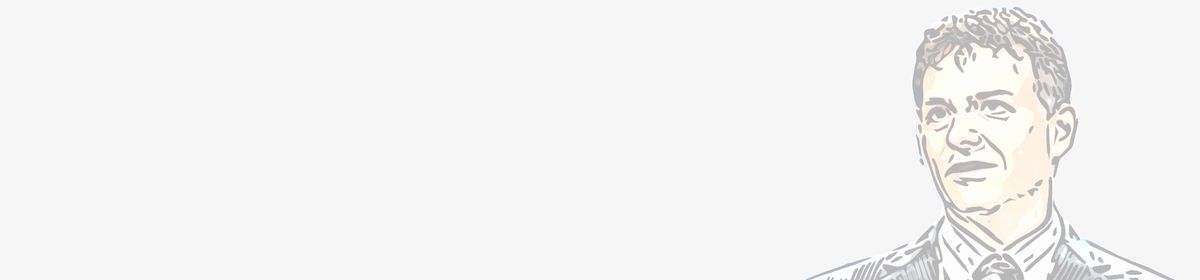もっとも、主たる論点は技術自体の評価ではなく、その技術が本当に利益をもたらすかにある。
書簡では、業界内での典型的な取引関係について仮の数字を置いて解説している:
- エンドユーザーがChatGPTを利用し年1ドル払う。
- ChatGPTを運営するOpenAIはMicrosoftに年2ドル支払いAIインフラを利用する。
- MicrosoftはCoreWeave(クラウド)からGPUを年0.60ドルでリースする。
- CoreWeaveは設備投資のためNVIDIAに2.40ドル、他に2.40ドル支払う。
こうした構造では、初年度に合計8ドル以上の売上が上がることになる。
支出のうち大きいのはクラウドの設備投資4.80ドルだが、これは時間をかけて減価償却費として計上されていく。
つまり、全体で見ると、売上は手前で多く計上され、費用は均等に計上されていく傾向にある。
さらに、手前で計上される売上の大半がAI利用者からではなく業界内からの売上になっている。
中にはいわゆるベンダー・ローンのように代金が出資の形で支払われる例も多くなっており、その場合、売り手の側にもリスクが残ることになる。
投資(裏返せば減価償却)に見合う売上が今後AI利用者から得られ続けなければ、費用だけが後に残るか、減損を強いられるかとなる。
書簡では、現在進行中の投資額は「とても極端」なレベル、つまり最終需要に対し過大であろうと述べている。
AIが最終的にすべて期待通りとなった場合でも、このサイクルを通しておびただしい金額の資本破壊が起こる可能性が相応に存在する。
書簡では、2000年までのインターネット・バブルさえ現在と比べれば強気ではなかったと回顧している。
経験上、潮目が反転する時はとても早く起こり前触れもない。
25年経った今でも、なぜインターネット・バブルがあのタイミングで弾けたのか明らかでない。・・・
現在の市場は私たちが経験した中で最も割高であり、警戒を続ける以外よい選択肢は見当たらない。