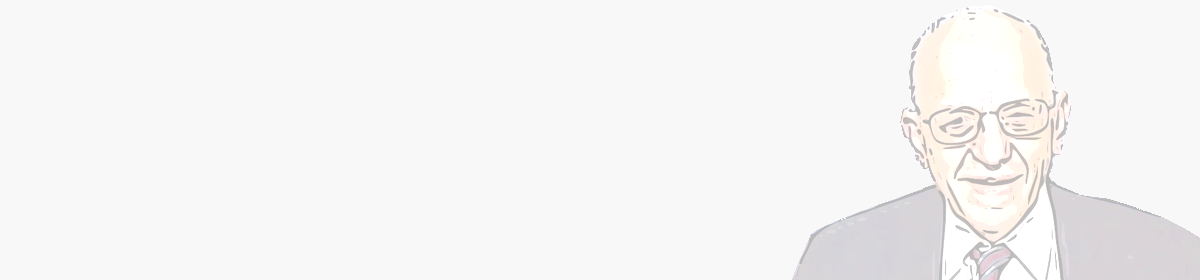ジェレミー・シーゲル教授が、堅調な米経済・インフレに太鼓判を押している。
また、新任のスティーブン・マイランFRB理事の講演原稿にも言及した。
今週後半の最も重要なニュースは昨日(25日木曜日)だった。
米耐久財受注はかなり強く、貿易赤字は予想をはるかに下回った。
シーゲル教授はウィズダムツリーのポッドキャストで、米経済が第3四半期も堅調だと解説した。
インフレの面でも、26日発表のPCEデフレーターが予想どおりだったとし、米国株市場は現状を好感していると話した。
トーンは総じていつもの強気のシーゲル教授だ。
このポッドキャストで特筆すべきは、教授がマイランFRB理事の講演原稿(22日ニューヨーク経済クラブ)に言及したことだ。
(同氏は、ヘッジファンド時代にいわゆるマールアラーゴ合意を提案したが、現在は提唱していないと言っている。)
大統領経済諮問委員会委員長を兼務しつつFRB理事に就任したマイラン氏は、今や最もハト派のFOMCメンバーとなった。
この講演原稿では、様々な要因(最も大きく効いているのは不法移民の減少による人口増加率の低下)により米国の実質中立金利がほぼゼロになっていると主張。
これから示唆される名目FF金利はテイラールールでは2.200-2.25%、各種補正を考えると2.0-2.5%になると書かれている。
シーゲル教授はこれを「とてもよく書けた論文、とても学術的な論文」と評価しているが、結論には同意していない。
「私はこれ(マイラン氏の示唆するFF金利)を信じない。
私は、FRBが3.25%まで利下げすべきと信じている。」
利下げが必要という結論こそ共通しているが、程度の問題については同意できないということだろう。
それもそのはず。
米実質中立金利が低下しているという主張は、米経済の潜在成長率が低下し、米市場の魅力が低下しているとの方向性を暗示している。
《永遠のブル》が受け入れられないのも当然なのだ。
シーゲル教授は、この乖離を埋めるため、従前からAIによる生産性上昇への期待を繰り返している。
この主張は、経緯こそ違えど、日本人にある種の既視感を与えるかもしれない。
移民政策を厳格化あるいは適正化すると(その是非は別として)人口動態の面では不利になる。
潜在成長率は上がらず、実質中立金利は低下し、ゼロ近傍に。
これが金融政策において低金利政策、実質ゼロ金利またはマイナス金利政策を正当化する。
従前から苦しかった財政問題は低金利のおかげで一息つくが、それが財政規律を弛緩させる。
金利低下によりいったん名目資産価格が上昇することもあるが、金融緩和をやり切った後は国債をはじめとして国内資産の利回り低下により、投資妙味は減退する。
ちょっとしたショックで国内資産・通貨が売られ、通貨安に。
それがインフレを招き、実質賃金の重しになる。
インフレや通貨安は財政や貿易にはプラスに働くが、国民生活は困窮する。
まさかそんなことはないだろうが、米国が日本化している可能性も捨てきれない。
日本の投資家にとって怖いのは円安ではなく、円安ドル安なのではないか。