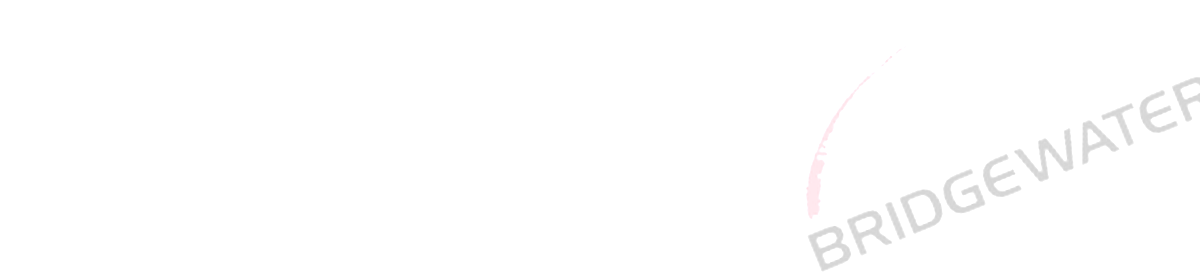ブリッジウォーター・アソシエイツが、急騰して一服した金相場について解説・予想している。
金がより重要な準備資産になるとの変化は必ずしもドルが準備通貨としての地位を失いつつあることを意味しているわけではない。
ドルにはいくつもの特質がある:
世界貿易の主要な決済通貨であり、債務の建値の主たる通貨であり、いまも貯蓄がなされている。
これらすべての観点で、金はドルに置き換わろうとはしていない。
ブリッジウォーターのデービッド・トリン氏が自社ポッドキャストで、金価格上昇の背景について冷静に分析している。
人々が金を保有する理由にはインフレヘッジや富の保蔵手段など様々で、今回の金価格上昇の主因を、人々が米政府のコントロール下にない富の保蔵手段を求めていると解説した。
金を買う人々の目的がインフレヘッジだろうと、富の保蔵手段の多様化であろうと、保蔵する価値が(ある程度)維持されることが前提になる。
そこで関心の的となっているのが各国の財政問題だ。
トリン氏は淡々とメカニズムを解説する。
「大きな財政赤字であっても、その大きな財政赤字に対応して中央銀行が適切に引き締め政策を実施するならば問題ではない。」
まさに昨年までFRBがやってきたこと、今も日銀がやろうとしていることだ。
つまり、財政拡大は金融引き締めとのセットなら問題とはなりにくい。
では、その時何が起こるか。
「もしも政府が大金を借りて中央銀行が金利を引き締めれば、基本的には経済の信用量が維持される。
政府支出の余地を作るために民間セクターが借金できないようになる。」
トリン氏は「均衡的経済状況」が実現し、経済成長とインフレのバランスが可能になるという。
これは教科書通り。
いわゆるクラウディング・アウトが起こることで均衡に達するのである。
ただし、均衡はとれるとしても、クラウディング・アウトを望む人は皆無だろう。
同氏も、これが選択されば民間セクターにとって「とても苦痛に満ちたプロセスになる」と予想する。
実際、世界の情勢はこの方向性ではないように見える。
「だから、とても大きな財政赤字とともに、まだ健全な民間セクターの信用創造が進んでいるケースがあり、それがインフレ圧力への心配を生んでいる。
財政赤字がマネタイズされて、今のお金が将来価値を維持できないとの心配を生んでいる。」
(次ページ: 中央銀行だけでは説明できない4,000ドル台)