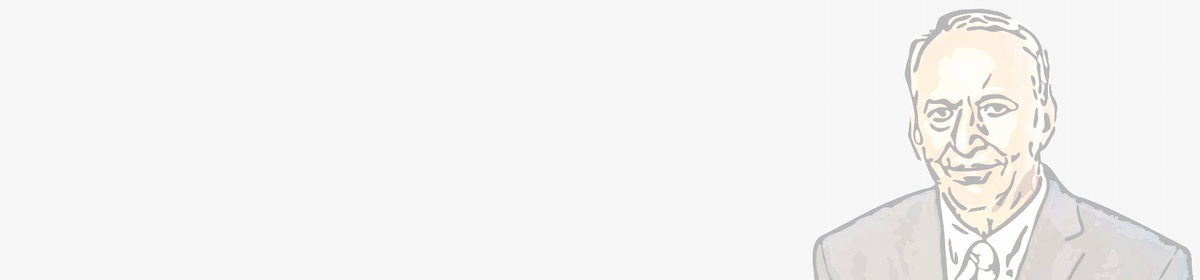今月初め突然台湾ドルが急騰したことが注目されている。
台湾という輸出経済に何が起こったのか、モルガン・スタンレーとローレンス・サマーズ氏の意見を聞いておこう。
5月2日、台湾ドルは1日での上昇として1980年代以降最大を記録し、2日で6.5%も上昇した。
台湾ドルは通常はボラティリティが小さいが、これはとても大きな変動だった。
モルガン・スタンレーのジェームズ・ロード氏が自社ポッドキャストで、月初の台湾ドルの急騰について言及した。
同氏はこれには2つの原因があったと考えている。
- 貿易交渉を鑑み、台湾輸出企業が台湾ドル高誘導を見越して一斉にドル預金を売却した
- 台湾企業の株がいくらか買われた
モルガン・スタンレーは、今回の台湾ドル高について、通商交渉が為替相場に与えた要因を大きく見ているようだ。
モルガン・スタンレーでは、移民の制限・財政問題・関税により米経済の鈍化を予想しており、来年2026年FRBがFF金利を2.5%程度まで引き下げると予想している。
CME FedWatch Toolによれば、市場が織り込む来年12月のFF金利は3.00-3.25%のところが最頻値となっている。
つまり、来年末についての市場の利下げ幅織り込みは過少と見ているため、ドル安を予想しているという。
また、今後通商交渉が進められ、ある程度の合意が形成されていくとするものの、「そのほとんどは休止と継続交渉という結果に留まり、不確実性は完全には払拭されない」と予想している。
台湾ドル急騰についてのモルガン・スタンレーの解釈は、通商交渉に絡んで輸出者がドルからエグジットした点を重視していた。
ローレンス・サマーズ元財務長官は、経済の仕組みによってなるべくして起こった可能性について言及している。
同氏はBloombergで、台湾が特有の状況(安全保障・ペッグ通貨・ヘッジ)下にあると前置きをした上で、対米貿易黒字と対米債権の関係から1つの可能性を示した。
「政権は、貿易黒字を憎むことと資本流入を好むことの矛盾を完全に明確には認識できていないようだ。」
米国への資金流入は、他国の対米貿易黒字の結果起こるものであり、資金流入を維持しつつ貿易赤字を縮小するのには無理があるとの指摘だ。
米国が貿易赤字を縮小すれば、米国への資金流入が細り、米国債需要が低下するのはある程度必然と考えるべきなのだ。
私が推測するのは、台湾の状況は特有のものではあるが、米国が直面する資本流入と貿易赤字についてのはるかに幅広い課題を示唆するということ。
1つわかっているのは、米国への外国資本の流入を減らすことなしに、単なる算数だけで貿易赤字を完全に解決することはできないということだ。
米ドル相場は、トランプ政権が関税について軟化の兆しを見せた(り見せなかったりした)ことで、7日頃から持ち直している。
仮に、米政権が本当に貿易赤字を大きく削減する意思を持ち続けているなら、特に対米債権国の通貨に対するドル相場はまだ先の見えない状況に置かれ続けるのだろう。