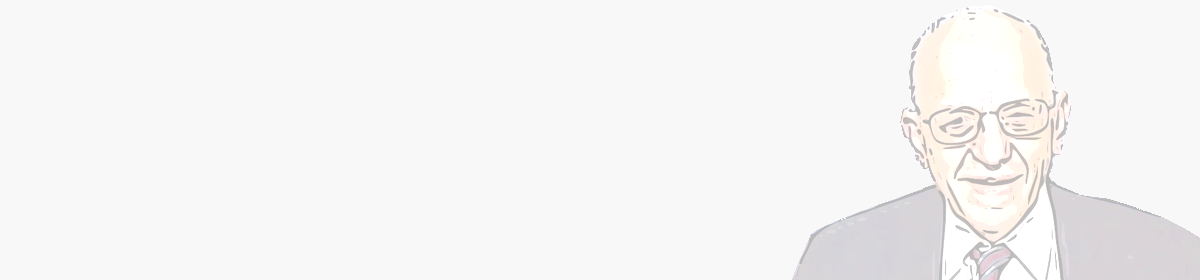ジェレミー・シーゲル教授が、トランプ関税への批判を続けつつ、米国例外主義と米国株市場についてコメントしている。
「中国に対して何を恐れているのか?・・・
中国経済が米経済より大きくなることなら、そうなると保証する。
人口は4倍で、現在の1人あたり国民所得は1/4しかない。・・・
中国は世界最大の経済になる。」
シーゲル教授がウォートンビジネスラジオで、引き続きトランプ関税とその背景にある考え方を批判している。
シーゲル教授は、米国がこれまで中国製品を輸入していたのは「はるかに安かった」ためと説明。
仮に中国から輸入しなくとも、他の国から輸入することになるだけで、切り替えには時間と苦労が必要になるという。
シーゲル教授は、仮に米国が国外からの輸入を完全に絶った場合、国民所得が低下し、厳しい景気後退になり、慢性化すると予想している。
「実質所得がおそらく5、6、7%下がるだろう。
ただし、そこからは成長できる。
でも、こう言うことになる:
以前は外国が安く作ってくれていたが、今は自国で作らないといけなくなり、それほど安くはできないだろう。
だから、豊かにはならない。」
長い年月をかけて増やしてきた自由貿易の恩恵を一度に吐き出すことになる。
重商的な貿易論の限界を指摘したものだろう。
過度に自国での生産にこだわり、関税や非関税障壁で守ろうとすれば、こうした弊害が出る。
それは保護主義を続けてきた国も同様だろう。
ディスインフレの時代なら取り繕うこともできようが、インフレが起これば、実質賃金の低下で国民は貧しくなってしまう。
シーゲル教授は特に、基軸通貨国の貿易赤字は自然なことであり問題ではないと話している。
教授は2日の「解放の日」を「流動化の日」と呼んでいる。
経済や市民の豊かさだけでなく、米国株市場の優位性も失われるのかとの問いについては、皮肉交じりに優位性は「6週間前まで」と答えている。
ただし、本音、長期では米社会の優位を確信しているようだ。
(教授は現政策が次の大統領に覆されると考えている。)
「米市場は世界一高い市場であり、米国例外主義という見方がある。
それは終わっていない。」
シーゲル教授は今も米国が起業家精神を尊び、それに資金を付け、新たなアイデアの追及を奨励し、世界中から優れた人材を引き付けていると指摘。
これら長い間『米国を偉大に』してきた状況は継続していると話す。
問題は、米国例外主義が米国株市場の高バリュエーションを正当化できるのかだという。
米国のPER 22倍と欧州の15倍の差はそれに見合うのか?
以前から言ってきたことだが、PERの差は利益成長の差に比べより重要になっている。
ポートフォリオによるが、利益成長は短期的にはとても重要だが、PERはとても重要、長期では最も重要になる。・・・
諸外国のPERはまだはるかに低く、長期ではそれら市場を諦めていない。
特に過去6週間の出来事があったからね。