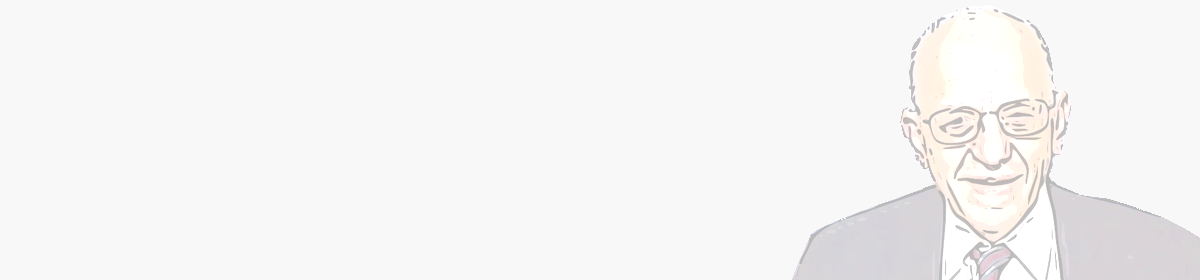ジェレミー・シーゲル教授が「株価が高すぎる」と口にするのは、仮に一時的な評価だとしても珍しいのではないか。
そのためか、教授はポッドキャストの最後に、基本的な主張である長期投資推奨につながる話を付け加えている。
株価は歴史的に景気後退に対して常に過剰反応する。・・・
しかし、そういう下落は合理的ではなかった。
景気後退が終われば、株価は戻るからだ。
過去を見返すなら、日本・欧州・新興国市場では株式市場が絶好調の後にとても長い停滞を迎えた時期がある。
ところが、米市場では少なくとも名目株価についてあまり長い停滞を経験していない。
(実質ベースでは1970年代がそうだった。)
したがって、米市場では景気後退と弱気相場を無視して長期投資をすることが可能だった。
さらに過去15年は押し目買いが必ずすぐさま報われるような相場だった。
だから、買ったままにしておけばいいという話になる。
シーゲル教授は数字入りの経験則を付け加えた。
景気後退入りのシナリオを信じる場合でも、正統的ファイナンス理論から言えば、株価は20-25%も下がらないはずだ。
みんなが谷の先の山を見通すかどうか見てみよう。
米国の景気後退は高々数年で終わることが多い。
しかも企業の利益の落ち込みは比較的浅い。
だから、永久期間のキャッシュフローの割引現在価値、つまり理論株価はそれほど低下しない。
それに対して株価の方は過剰反応し、もう少し大きく落ち込む。
これを聞いて、長期投資への意思を強めた人もいるだろう。
一方で、過剰反応がかなりよい経験則なら、マーケット・タイミングを試みようと考える人もいるかもしれない。
(つまり、今ショートしないまでも、例えば25%超下げた時には買うなど。)
ただし、これをあまり広く一般化してとらえるべきではないだろう。
例えば、日本では景気後退期の企業利益の落ち込みの幅が大きく、より大幅な株価下落が正当化されうる。
米市場にしても過去のままであるとは限らず、実際大きな変化を予想する人も増えている。
とりわけ米ドルが長期的に減価するようなら、名目株価が下がらなくとも、あるいは米国債に対して米国株がアウトパフォームしても、決してよい結果にならないかもしれないからだ。
(5日16:50 指数の数値の誤りを修正しました。)