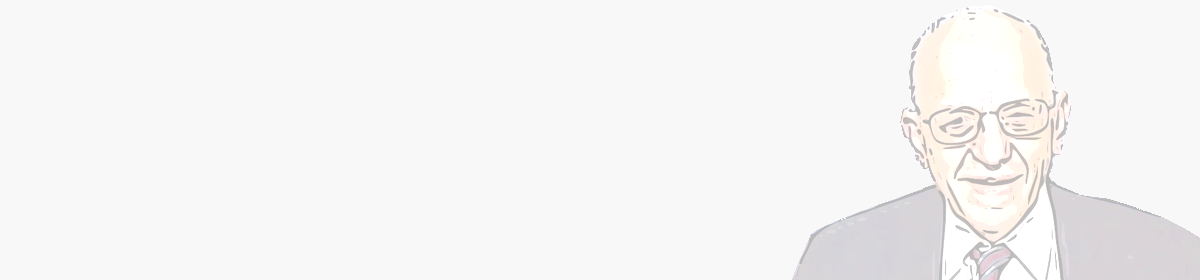今回シーゲル教授は、超過準備への付利が短期金利の変動を過度に抑制していると指摘している。
これは金利の本来のあり方ではない。
歴史を通して短期金利は長期金利よりもボラティリティが高く、信用市場の変化に対する緩衝材の役割を担ってきた。
今日では、短期金利が固定されているために、経済見通しの変化に対する(市場の)調整のすべてが長期金利の方に表れる。
シーゲル教授は、短期金融市場の金融調整機能を回復させ、FRBが短期金利の発するメッセージに耳を傾けるべきと考えているようだ。
2021年にFRBが利上げで出遅れたことを挙げ、仮に短期金利が過度に固定されていなければ、記録的な信用需要が短期金利を押し上げようとし、FRBはもっと早く利上げの必要性に気づけたはずと論じている。
そして、短期金利を強く固定しているのが超過準備への付利であり、付利が必要とされる理由はFRBの大きなバランスシートにある。
だから、バランスシートの正常化(あるいは量的引き締め)を進めるべきとなる。
この議論にはいくつもの論点がある:
- 金融市場の市場原理・機能の回復
- 長期金利の安定
- 金融政策の正常化(FRBバランスシートの縮小)
- 超過準備への付利引き下げによるFRB財務の改善
- 市中銀行への事実上の利益供与の終了
これらに問題がないと考える人はむしろ少ないはずだ。
それでもFRBバランスシートの縮小が一足飛びには行かない背景には、進め方の難しさがある。
そもそも超過準備への付利が始まったのは、FF金利が誘導目標よりも低下しないようする必要からだった。
リーマン危機への対処として導入された量的緩和によって市中銀行は莫大な流動性を受け取ることになった。
仮に超過準備への付利がなければ、市中銀行は受け取った資金を金融市場に振り向けることになり、これが市場を中央銀行が求める以上に緩和してしまう。
シーゲル教授も、拙速なバランスシート縮小の危うさは心得ている。
仮に今、一気にバランスシートを縮小しようとすれば、FRB保有の国債売却が国債市場を混乱させる。
超過準備への付利をなくせば、市中銀行は準備預金を減らし短期債を買おうし、短期金利が急落、インフレ昂進を引き起こしかねない。
教授の処方箋はこうだ:
FRBが少額の準備預金の体制の恩恵を得る1つの方法は、超過準備への付利をある一定の水準だけ例えば2%ポイントFF金利誘導目標より低く設定しつつ、少額の(超過)準備預金に戻すために法定準備率を引き上げることだ。
こうした政策は短期信用環境の指標としてのFF金利市場を復活させ、市中銀行への利払いを削減し、FRBの収益性を回復させる。
このアイデアは、異次元緩和がまだ華やかなりし2016年に元日銀理事 早川英男氏が予想していたもの、そのものだ。
法定準備率を引き上げるとは、同じ準備預金を積んでいても超過準備とする金額を小さくすることであり、付利される金額が小さくなる。
(つまり、バランスシートをさほど縮小しなくても、同様の効果を得られるということ。)
これは正常化の痛みを市中銀行に一部転嫁するものであり、ある種の課税(あるいは補助金の削減)のような変更になる。
シーゲル教授はこの点について、規制緩和を進めることで市中銀行にそれ以上の恩恵を与え相殺できると主張している。
また、付利をFF金利の2%ポイント低くしろとは、仮にFF金利が誘導目標より低下してしまっても、それぐらいの金融緩和は問題にはならないという感覚を教授が持っているということではないか。