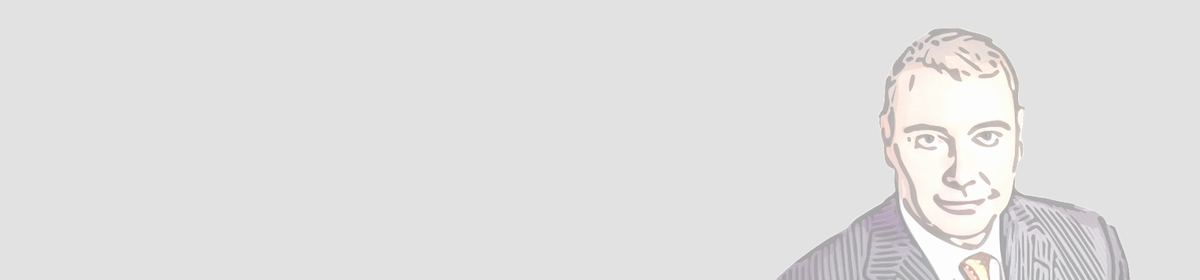ダブルライン・キャピタルのジェフリー・ガンドラック氏が、変質した米金融政策をディスっている。
赤の期間が公式な景気後退を示している。
2%の長期平均インフレ率が目標とされていた頃を思い出せ。
今から数年デフレが必要になるはずだ。
それを見込んではいけない。
債券王ガンドラック氏がツイートした。
Red bars are official recessions.
Remember when 2% long term average inflation was the goal?
Need deflation next few years to get there. Don”t count on it, pic.twitter.com/DXcZIPvBl4— Jeffrey Gundlach (@TruthGundlach) September 24, 2025
米金融政策を回顧しよう。
2008年のリーマン危機後、FRBはデフレを解消・防止するために2%のインフレ率目標を設定した。
デフレ(ある程度継続する物価下落)は有害だから、これにゼロ金利+量的緩和で対応したのは妥当だったろう。
デフレ(継続的物価下落)から脱した後も、インフレ率にマージン(2%)が欲しいとして金融緩和が続いた。
これも妥当だったろう。
しかし、その後、米国には慢性的な金融緩和漬けの症状が出てくる。
いくつかのインフレ率が2%近傍になっても、FRBが重視するインフレ率がまだ2%未満だとの理由で金融引き締めを先延ばしにした。
FRBが重視するインフレ率が2%に近づいてくると、今度は物価水準目標(price level targeting)へのすり替えを行った。
物価水準目標とは、足下のインフレ率ではなく、インフレ率の中長期平均を2%にするという目標設定だ。
近時の過去に2%を下回る時期がある場合、過去の未達分を将来2%に乗せて取り返さないといけないという考えだ。
わからなくもないが、長い金融緩和を疑問視する向きからすれば、単に金融緩和を続けたいための言い訳に響いたろう。
これはまた、パンデミック後のインフレ急騰に対しFRB利上げが遅れる一因となった。
物価水準目標を受け入れるなら、平均で2%のインフレ率を達成することを求めることになる。
これが達成されると、物価の現指数は毎年2%上昇するトレンド線(図中の赤の点線)の近傍にあり続けることになる。
ところが実際の現指数は青線だ。
パンデミック前後の短い景気後退期の後ほどなくして2%上昇トレンド線から大きく上方に乖離している。
物価水準目標が堅持されるには、早急なデフレが必要というわけだ。
もちろん、ガンドラック氏はトレンド線への回帰を予想していない。
同氏が予想するのは、かつて理想とされた物価状況よりはるかに上振れした物価の継続だ。
米政府はそんな時に高率の関税を課し、FRBに利下げ圧力をかけている。
(関税の悪影響でデフレを狙ったわけでもあるまいし・・・)
米市場が両極端(株式の楽観、金への逃避)に分かれているのも納得がいくだろう。