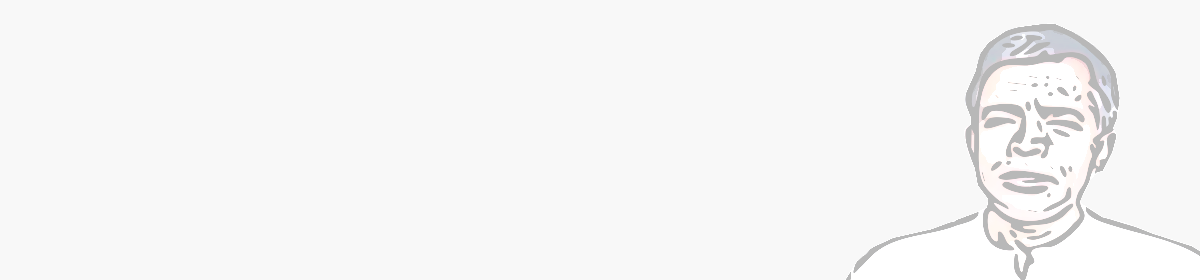アスワス・ダモダラン ニューヨーク大学教授が、シラーCAPEレシオを用いたマーケット・タイミング戦略の有効性についてバックテストを行い検証している。
ダモダラン教授が自身のブログで、今年これまでの3四半期の米国株市場について回顧した上で、米株価の高低について議論している。
高低を議論するというより、高低を判断するための指標について議論したというべきか。
教授はまず明らかに不十分な指標を3つ挙げている: 過去の株価推移、PERなどバリュエーション、イールド・スプレッド。
後のものほど多くの情報を取り込んでいるが、それでもかなり荒っぽい指標である。
ダモダラン教授は、結局のところ、インプットを丁寧に選択したDCF(またはそこから逆算されるインプライド株式リスクプレミアム)によるべきと示唆している。
教授の結論はこうだ:
現在の市場がPERから益回り、イールド・スプレッド、株式リスクプレミアムのような本質的価値の尺度に至るまですべての数値において高く(Richly)値付けされていることは否定できない。・・・
過去平均への中央回帰を信じるのなら、株式が実際に割高であり調整が迫っていると結論するのが理に適っているように思える。
ここでは、その結論に至る場合でも、それを行動に移すことが難しい理由を検証する。
つまり、割高・割安を判断できたとしても、それを投資行動に移してリターンを得るのは難しいと言いたいのだ。
ここからが本題だ。
ダモダラン教授は米市場における次のようなマーケット・タイミング戦略を検証している:
- 価格指標: シラーCAPEレシオ
- トリガー: 過去のCAPEレシオのメジアンより25%下で買い、25%上で売る。
- 配分ルール: 標準を株式60:債券40とし、25%下で80:20に、25%上で40:60に変更。
このルールに基づき、1871年から2025年について(税金・取引コストを無視したベースで)60:40ポートフォリオとのリターンの差を計算している。
結論から言うと、長期的に見て有意な差は見られないというもの。
ダモダラン教授は異なるパラメーターでも検証しているが、同様な結果となっている。
(ありがたいことに、読者が様々なパラメーターで検証できるようスプレッドシートを公開している。)
この結果にサプライズはない。
CAPEレシオに実利的な予見性がないことはすでに知られていた事実だ。
ただ、実際の数字を鑑賞すると《マーケット・タイミングはうまく行かない》という世間の常識を改めて信じたくなるものだ。
もちろん、異なるタイプの価格指標、トリガー、売買ルールを設定すれば、結論が変わるのかもしれない。
ダモダラン教授も、ここでの一応の結論を読者に押し付けるつもりはない。
ただ、こうしたバックテスト(実際データを用いたシミュレーション)から得られる3つの教訓を読者にアドバイスをしている。
- 価格指標: 不完全な指標を用いれば、永遠に調整が起こらない可能性が増える。比較的優れた指標を用いても経済・市場の根本的変化は感知できない。
- 有用性の判断: 統計的手法(相関や回帰分析)ではなくバックテストによって実証すべき。
- ノイズと欠陥: 最善を尽くしても「市場はあなたが破産せずにいられるより長くミスプライスを続ける可能性がある」。