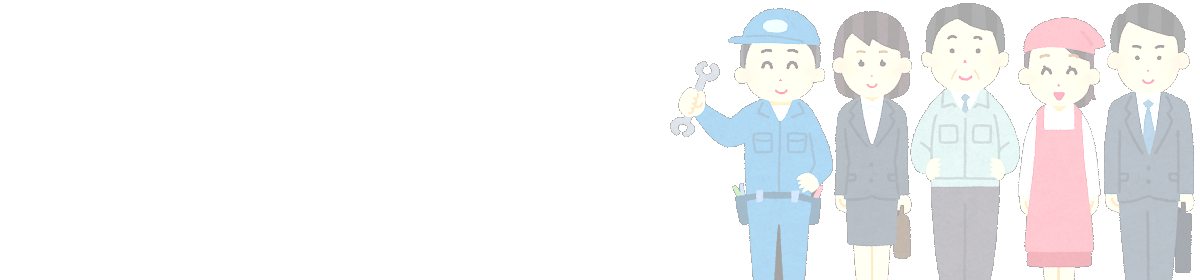米CNBCが「あなたの引退計画が失敗しかねないワケ」と題するビデオを公表している。
問題を端的に率直に語っているところに共感が持てる。
「調査では、アメリカ人の64%が死ぬことよりも引退後にお金が尽きることの方を心配していることがわかった。
調査対象のアメリカ人の1/4が引退できないと信じている。」
CNBCがキャッチーなファクトで始まるビデオを公表した。
米国例外主義などが信じられている国にしては、あたかも日本のことかと聞き違えるほど景気の悪い響きがある。
ビデオでは若い世代に待ち構える苦境を暗示するいくつもの観察・分析が紹介されている:
- 半数以上の人が計画より早く引退している。
50代で職を失う人が増えている。 - 社会保障に依存する人が極めて多い。
長く働いても、恩恵の多くはすでに引退した世代に。 - 社会保障に頼れないとして上の世代より貯蓄を増やしている(Z世代)。
企業年金への加入者は(401kへの制度変更で)15%のみ。
持ち家による財産形成が困難に。
上の世代より資産は少ないが、世代内での格差が大きい(ミレニアル世代)。
学生ローンを必要とする割合が増大。 - 米社会保障は7年以内に破綻の危機に。
政治家は問題を先延ばしにし深刻化させる。
いずれもどこかで聞いたことのあるような話だ。
これがアメリカン・ドリームの国の実態のようだ。
ドリームを感じさせるところが格差拡大だけなのがなんとも悲しい。
ビデオはさらに悲しいファクトを畳みかける。
「調査対象となったまだ引退していない米労働者の70%が引退時期の後倒しを検討していた。
調査対象の半分近くが、十分なお金が得られない恐怖に言及し、インフレを心配していると答えた。」
遠い昔から、インフレとは投資家にとっての最大の脅威と言われてきた。
足下で一時インフレが起こるならそれはリスク資産価格上昇の要因となるが、基調的なインフレ上昇は(実質成長が上昇しない場合)名目資産価格を上げることはあっても実質の購買力・投資価値を損ねてしまう。
平均余命が長くなり、まだ長い長い人生を生きる世代にとって、インフレの恐怖とは底なし沼のように感じられるのかもしれない。
かつて引退年齢とされていた60歳前後の人にさえ、今や長い長い余命が待っているのだ。
ビデオでは、大まかな結論が導かれている。
ありふれた結論であるが、長く働き続けること、というものだ。
ビデオ内でNew School For Social Researchの教授がこう言っている:
「もしも働きたいなら働けるようにしないといけない。
それが社会の価値というものだ。
年齢に制限をかけず、最終的には政府が雇えばいい。
すべての労働者に雇用を保証しなければいけない。」
ベーシックインカムや生活保護のように単にお金を配るというような話より、はるかに理に適ったアイデアだろう。
一方、CNBCは、年寄りが働き続けることの弊害についても目配せをしている。
いわゆる老害のリスクだ。
これについて、先述の教授はやや理想的すぎるストーリーを述べている。
世代間で助け合う職場を、といった感じだ。
このストーリーは正直絵に描いた餅の域を出ないが、次の発言は的を射ている。
「長く働きたいなら、2つの側面、2つのグループがいる: 企業の側と労働者の側だ。・・・
あなたが労働市場を必要とする時、労働市場がいつもあなたを必要とするとは限らない。
あなたが働くか否か、あなたの仕事の質を決める最大の役割を担うのは企業だ。」
企業がいつどれだけ労働者を必要とするかは経済や業界の景気次第だから、企業に過大に雇用の義務を負わせるわけにもいかないだろう。
そして、企業とは、その時必要な駒を安く雇おうとする習性がある。
「仕事の質」を決める権限と責任を担うのは一義的には企業の側にあるし、雇う量に比べれば、こちらの方にはまだ工夫の余地があるのではないか。
FPの読者の中にはいわゆるFIREを目指す人も多いようだ。
仮に、若い世代も年寄りの世代も「仕事の質」や公平感にそこそこ満足できるような企業になれるなら、そもそもFIREを目指す人も減るように思えるし、体が動く限り働こうという意欲を持つ年寄りがもっと増えるのではないか。
もちろんそれが難しいから今があるのだろうが、ここにはまだ工夫の余地があるように思える。
少なくとも日本は今人手不足なのだ。