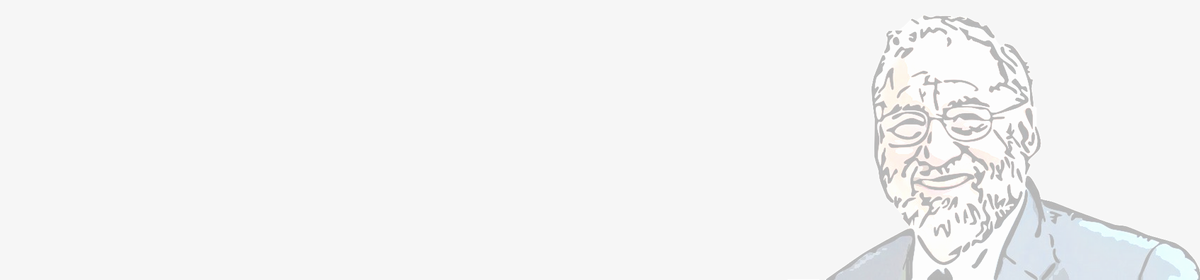ジョセフ・スティグリッツ教授が、事実上のグローバル・ミニマム課税の頓挫について憤りをあらわにしている。
OECD/G20包括的枠組みのメンバー国は、G7での合意を拒否すべきだ。
米国が世界の政策を規定するのを許してはならない。
米国は強力だが、それでも世界のGDPの20%未満でしかない。
スティグリッツ教授がProject Syndicateで、トランプ政権の専横、G7各国の弱腰を批判している。
ここで議論されている「OECD/G20包摂的枠組み」とは、大手多国籍企業に対し利益を申告した国ではなく事業を行っている国で公平な税金を支払うよう求めるもの。
2つの柱からなる:
- 対象企業が物理的な拠点を有していなくても、大規模な顧客基盤を有する国に課税権を持たせる。
- 最低15%の法人税率(グローバル・ミニマム課税)を適用し、低税率による企業誘致を防ぐ。
つまり、大企業のタックスヘイブンによる課税逃れを防ぎ、各国政府による低税率による底辺への競争を防ごうというものだ。
世界のほとんどの国々で財政悪化が進む中、小さな税収や雇用の取り合いによって各国政府が取るべき全体のパイが減っている現状を打破しようというものだった。
スティグリッツ教授は、低税率による過度な誘致合戦がほとんど新たな投資を生まないこと、専ら最も金持ちな企業を太らすだけに終わることを問題視してきた。
こうした問題意識は広く共有され、2021年10月には140か国が合意している。
これに対し、今年1月トランプ新大統領が就任すると、米企業に不利に働く「枠組み」に対して対抗措置を講じ始めた。
「大きく美しい法案」の第899条だ。
この条項は、米国が不公平とみなした外国の政府・企業・個人に対し、米国が報復として課税するというもの。
課税対象は利子・配当、米国事業による所得、不動産譲渡所得等々に及び、米国内の事業所得だけでなく広く投資家に対する課税で国際社会に脅しをかけたのだ。
自分たちの損得だけを行動の指針とする、ならず者国家のやり口であり、通商交渉においてデジタル収支を度外視して財の収支だけを俎上に上げるのと似た一方的な主張だ。
第899条は2つの意味で関心を集めた。
1つは、米国のいつもの傲慢なやり口に対する反感。
もう1つは、もしもこれが実行された場合、米国離れがいっそう加速するのではないかとの見方だ。
米国は自ら《法外な特権》を捨て去ることにはならないか、という観点だった。
先月のG7では、あっさりと6か国が米国に折れた。
「枠組み」において、米企業を例外扱いすることで合意したという。
また、カナダは先月末から導入予定だったデジタルサービス課税を撤回した。
各国とも米国との通商交渉への悪影響を恐れたのだろう。
結果、米多国籍企業は、今後もタックスヘイブンを利用した租税回避が可能になったのだ。
この合意を受けてベッセント財務長官が第899条の削除を上院共和党に要請している。
これにスティグリッツ教授が吠えている。
・・・再びG7各国は途上国・(多国籍企業が儲かると見たペテンを利用できない)中小企業・結果として税負担の増える自国民よりも多国籍企業の利益を優先することを決定した。
米国の利益誘導型政治にまた諸外国が敗北した。
ただし、これはMAGAを示すものではあるまい。
米国自体が急激な財政悪化に苦しむ中、自国の最も裕福な企業の租税回避継続に道を開いたのだ。
米帝国の凋落は意外と早く進んでいくのかもしれない、と考えるべきではないか。