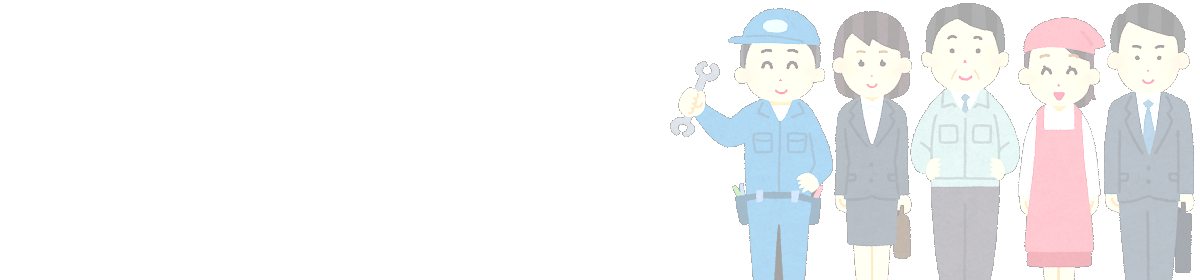米金融メディアCNBCが、悪化する米労働市場について分析し、今後の不安材料を指摘している。
「大学新卒は全労働者の中で見て良好な就職見込みを持つのが通常だ。
過去、新卒の失業率は低かった。
そのトレンドが2022年から反転している。」
CNBCが9分弱の特集ビデオで、近時の就職難について理由を探っている。
かつては全体に比べて低かった大学新卒の失業率が、全体を上回るようになっているという。
ビデオでは主因として、熟練を要しない仕事がAIによって消化されるようになったと指摘している。
16-17日のFOMCでは25 bpの利下げが決定された。
依然米インフレは目標を上回っているものの、雇用の急激な悪化を重く見ての判断だった。
CNBCは不安材料を指摘している。
「FRBの政策とは、循環的な問題に対処するために企図されている。
循環的なものであれば、FRBは時間をかけ趨勢の方に引き戻すことができる。
しかし、趨勢を変えることはできない。」
金融政策とは一義的には安定化政策に過ぎず、構造的な問題に対処するのに特に有効であるわけではない。
金融政策によって労働市場の趨勢、トレンドが変わることはないとの指摘だ。
CNBCはまた、もう1つの趨勢、トレンドについても言及している。
それは、減税・移民政策・関税などが影響を与えているインフレ基調の構造的・趨勢的・トレンド的な上昇だ。
「もしもFRBが今間違っていた場合、利下げによりインフレ的環境となり、高インフレという意味で多くの人々にマイナスのインパクトを与え、大いに苦しめることになるかもしれない。」
CNBCは決してFRBの利下げを批判しているわけではない。
ただ、今回の雇用悪化について、金融政策が最善の対処法ではない可能性を指摘している。
雇用が心配される一方、米株式市場は依然として最高値圏、絶好調だ。
FRBが予防的利下げに踏み切ったことと言い、1990年代を思い出す人も少なくあるまい。
当時はIT革命・インターネット革命というレトリックが市場を押し上げた。
今回もさらにメルトアップが進む可能性は大いにあるのかもしれない。
一方で、IT革命と叫ばれた時期は、米国で労働分配の低下が進んだ時期でもあった。
生産性上昇などの果実、ITの恩恵が労働者ではなく、資本に配分されたのだ。
さらにインターネットが普及したため、デイトレーダーといった生き方が浸透した。
ある意味、多くの人が労働者として分配を受けるより資本家として分配を受けようと考えを変えたのかもしれない。
それは当然ながら株式市場が心配の壁を登る後押しになったのだろうが、それも2000年に入って逆回転が始まった。
今回はどうだろう。