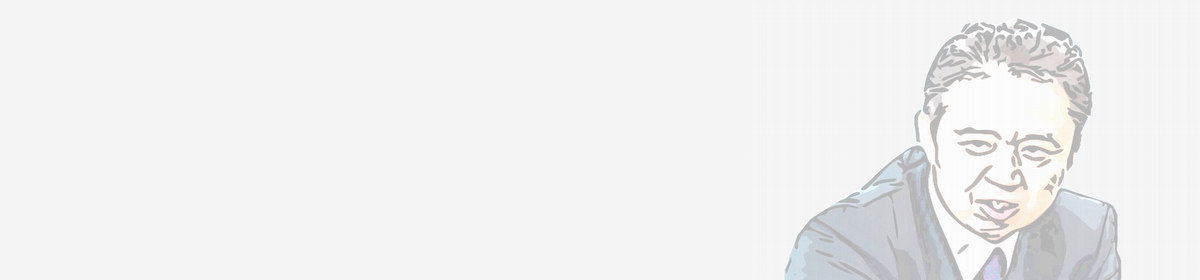ここで私たちが心得るべきは、多少のタイミングのずれこそあるものの、国債の価値の低下について現実的な見方をすることだ。
2013年から始まったアベノミクスでは協調的な金融・財政政策が採られたとされている。
しかし、実際には2020年のパンデミック対応までは比較的財政は抑え気味だった。
安倍政権もさすがにさらなる財政悪化には危機感を持っていたのだろう。
結果、前半は金融政策に偏った景気刺激となった。
それでも市場は当初、協調的という言葉を信じ、とりあえず円安(正確には円高の巻き戻し)で反応した。
一方、財政は急激な悪化とならず、金利はむしろ低位安定、つまり国債価格は安定していた。
イールドカーブ・コントロール実施後は当然ながらそれが続いた。
パンデミックに見舞われ、大規模な財政出動が採られたのは(方法(マスクの造りなど)の妥当性は別としても)当然のことだった。
問題はその後だ。
財政支出が高止まりすると、やはりインフレや通貨安になる。
さて、長期金利を再びペッグするとどうなるか。
これは財政が悪化する中で、それに反して国債の名目価格を維持しようということを意味する。
仮に日銀が国債利回り(つまり価格)のペッグに成功する場合、財政悪化により国債の価値が下落しているのだから、誰かが代わりに下がらなければならない。
代理となるのは、名目価格の尺度である通貨 円の価値である。
イールドカーブ・コントロールを復活させ国債の名目価格を安定させようとすれば、代わりに円の価値が下がる。
そして、再び輸入インフレが起こり、ホームメイド化されていくのである。
政権は決して口にしないだろうが、これは政府にとっても好都合だ。
国債のほとんどが国内で消化されている日本では、国債の債務者は政府、債権者は国民である。
円の価値の下落により国債の価値が下がるとは、国民の資産の減価によって政府の債務負担が減ることを意味する。
隠れた税金、いわゆるインフレ税であり、外国からも文句が出にくい。
《現在のインフレはディマンド・プルでなくコスト・プッシュだから金融引き締めで対応すべきでない》といった意見もよく聞かれるが、これは日本においては正しくない。
米国においては、すでに金融引き締め状態にあるから正しいのだが、日本ではいまだ金融緩和状態だからだ。
この金融緩和が円安の主因の1つとなっており、これがコスト・プッシュの主因の1つとなっている。
つまり、今や先進国でもトップクラスにある日本のインフレは確かにコスト・プッシュが主因だが、そのコスト・プッシュの主因の1つが金融緩和なのである。
こうした場合《コスト・プッシュだから金融引き締めで対応すべきでない》という論理は見当違いだ。
(だからこそ、日銀は歯を食いしばって利上げを続けてきた。)
しかし、金融緩和を望む政治勢力は今後もこの見当違いな主張を繰り返すだろう。
(次ページ: ガンズ&バターで起こること)