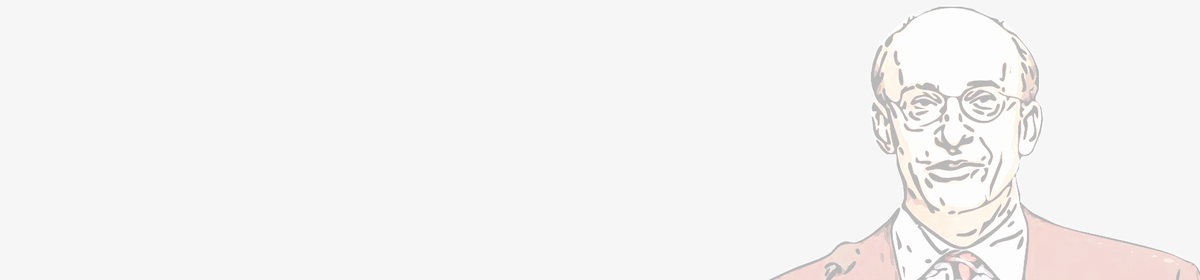元IMFチーフエコノミスト ケネス・ロゴフ ハーバード大学教授がFTのマーティン・ウルフ氏のインタビューを受けている。
トランプの経済政策に対する正統的な経済学による解説がなされているが、中から1985年プラザ合意についての発言部分を紹介しよう。
「以前、ジャンクロード・トリシェ(元ECB総裁)が数字を書き留めた紙を見せてくれたことがある。
円が10%上がるという想定を書いたもので、それが(プラザ合意)当事者の計画だった。
その後、当時財務長官だったジェイムズ・ベーカーと話した時、それが計画だったと言った。・・・
2週間で10%円高にするつもりだったが・・・『4週間後に25%上昇して制御不能になった』と言いながら笑った。」
ロゴフ教授がFTインタビューで、プラザ合意の舞台裏について話した。
ベイカー氏が笑ったというのはなんとも腹立たしい話だ。
日本は言い訳をすべきではないだろうが、プラザ合意こそ日本をバブルに誘い込み、崩壊後の長い停滞を生み出した出来事だった。
プラザ合意時のドル円相場は1ドル約240円。
合意直後から予想外に急激なドル安が進み、1987年ルーブル合意でブレーキが踏まれることとなった。
ルーブル合意時は約150円だったが、その後もドル安は止まらなかった。
急激な円高進行は日本経済に悪影響を及ぼした。
日銀は円高防止のために金融緩和を余儀なくされ、これが投機的な経済環境を生み出した。
結果、1980年代終わりの巨大バブルの大きな要因となった。
ロゴフ教授は当時の日本の状況をより深く見ていた。
プラザ合意と前後して、米国が日本に強く金融自由化を求めた点を指摘している。
米国は、日本がまだ準備不足だったのに規制緩和を強いてしまった。
日本がよいと考えるタイミングでやっていれば、その後の危機のようなことは起こらなかっただろう。
米国は完全に触媒の役割を果たしてしまった。
ロゴフ教授は、当時の日本が「米国に立ち向かうべきだった」と話している。
教授がこの話を持ち出したのは、言うまでもないが、いわゆる「マールアラーゴ合意」が実現されることのないよう願うからだ。
中でも、諸外国の外貨準備を米国が決める発行条件の100年債とスワップしようという、なんとも自分勝手な部分を問題視している。
「これはデフォルトだ。
米国はその債務をデフォルトさせようとしている。
ドルは自然と下落するので、ドル安を誘導する必要はない。」
ロゴフ教授によれば、米ドルの基軸通貨としてのステータスはすでに2015年前後にピークを迎えており、衰退を始めているという。
トランプ大統領は触媒の役割を果たし、衰退を大幅に早めているのだという。
教授は、今後起こることについていくつか気になる予想を述べている。
- 「米財政問題は解決しないだろう。」
- 「トランプは(財政問題が)解決したと宣言するが、市場は『バカげている』と言い、債券利回りは上昇する。」
- 「トランプ政権下で物価統制(訳注:ニクソン時代にあった)が実施されても驚かない。」
- 「低金利での預金を強いる金融抑圧があるかもしれない。」
もっとも、これまでの無理筋の政策から考えれば、この程度の資本規制ですむのならバンバンザイかもしれない。
このインタビューでは、米国で滅びつつある知性・節度ある保守派の考えを再確認することができる。
もちろん人それぞれ意見はあろうが、一読の価値のある内容だと思う。