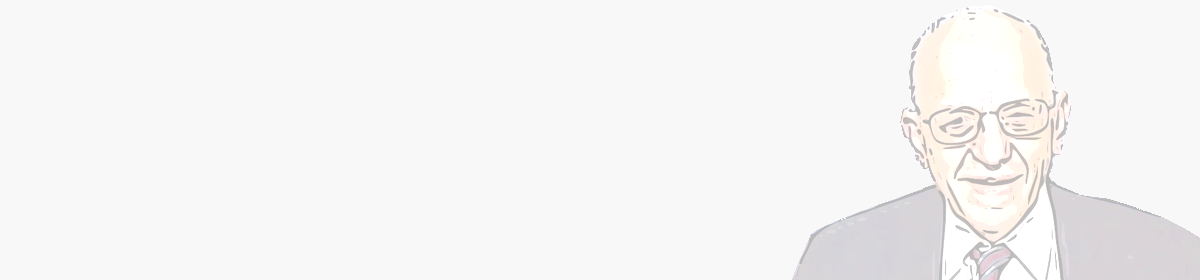ジェレミー・シーゲル教授が、米経済・市場に見られる3つの断絶について現実を語っている。
「いや、私は同意しない。」
シーゲル教授がCNBCで、現在の市場が1999年(ドットコム・バブルが佳境に入った頃)と類似しているとの指摘に反対意見を述べた。
教授は、当時との相違点として、PERがさほど高くないこと、実質金利が低いことを挙げている。
シーゲル教授は依然として強気だ。
市場のモメンタムはまだ続いていると指摘している。
ただし、一方で諸手を挙げて喜べない現実も認識しているようだ。
教授は、AIとそれ以外の濃淡を指摘する。
これは株価の話だけでなく、実体経済の話だ。
シーゲル教授は、経済・市場を牽引しているAI関連企業による雇用が全体の1.0-1.5%に過ぎないと指摘する。
これら2つの間に大きなギャップが存在する。
AI株は上昇を続ける可能性があり、仮に経済が試練を迎えても、インデックスへの投資家はうまくいく可能性がある。
シーゲル教授は「試練」をもたらしうるものとして政府閉鎖と関税を挙げている。
シーゲル教授はこれまで、トランプ関税や移民政策等の逆風をAIによる生産性向上がオフセットする可能性があると述べてきた。
仮にこれが実現すると、AI以外の部分を中心として労働者に対して逆風が吹く可能性がある。
過去を振り返っても技術革新の果実は往々にして労働でなく資本の方に配分されてきたのが現実だ。
教授の強気ロジック自体に、労働者、引いては米経済の重要なエンジンである個人消費への逆風が含まれていることになる。
シーゲル教授は、この出演で3つの「ギャップ」に言及した。
1つ目・2つ目は上記のとおり: AIとそれ以外、実体経済と市場。
そして3つ目は消費者だ。
「ハイエンド側の消費、株式市場、ビットコイン、資産価値が上がって懐の温かい人たちは支出している。
下の半分では支出に陰りがある。
だから、消費支出の強さを語る時には、どちらの消費者の話か断らないといけない。」