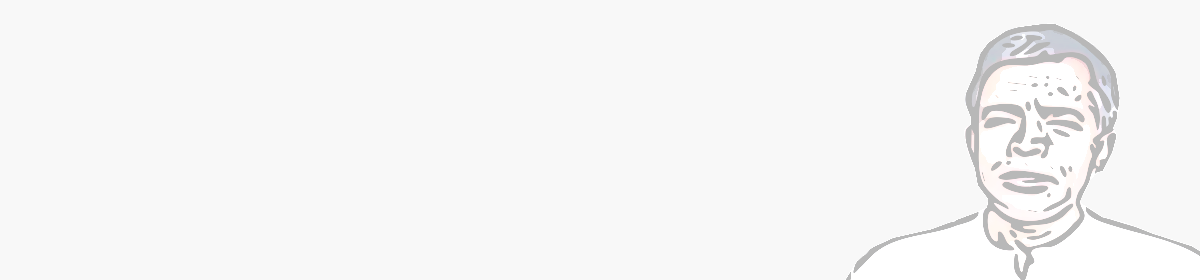アスワス・ダモダラン ニューヨーク大学教授が、株主還元の方法についての基本的だが重要なポイントを話している。
「配当も自社株買いも価値を生み出すわけではない。
いずれもキャッシュ・リターンをもたらすが、自社株買いは価値の移転を生み出しうる。」
ダモダラン教授がMotley Foolで、株主還元について教科書通りのレクチャーをしている。
MM理論を引くまでもなく、仮に株価が株式の根源的価値と一致しているなら(税務上の扱いを除いて)経済的効果はほぼ同じになる。
すべての株主(自社株買いの場合は売る株主と売らない株主)にとって(税負担を除き)損得はない。
しかし、通常、価値と株価は完全には一致していない。
(そもそも価値は一意に定まらない面もある。)
これが自社株買いにおいて富の移転を引き起こす。
- 株価>価値の場合、売らない株主から売る株主へ富が移転する。
- 株価<価値の場合、売る株主から売らない株主へ富が移転する。
ダモダラン教授は、当然の帰結を予想する。
「もしもどちらかの株主に忠誠を誓いたいなら、(売らずに)会社に残る株主に忠誠を誓いたいはずだ。」
だからこそ、自社株買いは、自社の株価が安いと思われた時に実施されることが多い。
究極のインサイダーである経営陣が《株価が安い》と考えている可能性と受け取ることで、一般の投資家は自社株買いを強気のシグナルとみなす。
自社株買いが基本的に価値を生み出さないにも関わらず好感されるのは、こうしたシグナリング効果によるものというのが教科書の教えだ。
しかし、実際に本当に割安な時だけに自社株買いが行われているのかと言えば、大いに疑問だ。
あるいは、株価と価値が一致することがレアケースと考えるなら、方向はどうあれ、自社株買いのほとんどは不公平な株主還元手段ということになる。
どうやら、ダモダラン教授はこの不公平性を問題視しているようだ。
株価と価値の乖離が大きい場合、教授は自社株買いでなく特別配当での還元が望ましいと話している。
普通配当でなく特別配当とするのは、投資家が配当について安定的なキャッシュインを期待するためだ。
特別配当と断ることで、投資家が増分の継続を期待せずにすむ。
ダモダラン教授は、投資環境の不確実性が高まる中、株主還元のあり方も変化すべきと考えている。
これまでは高収益かつ利益について予見可能な企業が多かったので、安定配当が可能だった。
そうした会社はどんどん減っており、柔軟な配当政策の必要性、現金を自社株買いと配当でどれだけ多く還元するか、が重要になるだろう。