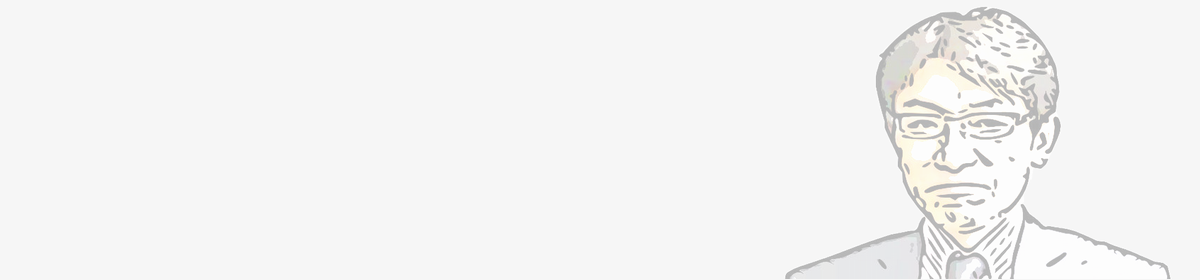河野氏の新著『日本経済の死角』に対する3つの所感の最後は「収奪的システム」が失敗だったのか否かである。
話はかなり戻るが、アベノミクスが始まる前後、このブログ(浜町SCIコラム)では随分と反対意見を書いていた。
理由は単純。
国民の購買力を奪い、貧しくすると信じていたからだ。
当時筆者はメーカーの事業開発の仕事を手伝っており、いわばメーカー側の当事者の1人としてアベノミクスを2つの面から解釈していた。
- 国際競争力: 国内で生産される財のコスト競争力を上げるために、国内で投入される資源、主には労働力と不動産、場合によっては資本を安くしたいのだろう。
実際、資本コストは相対的に低く抑えられてきたし、日本は他の先進国と比べて不動産価格の上昇も遅れ、かつ緩慢だった。
人件費も然りなのだろう。 - 政府と民間の債務・債権バランス: 政府は借金漬け、民間が直接・間接に政府に対し莫大な債権を有しており、持続性が懸念されてきた。
これを改善するには、民間から政府への富や所得の移転が必要なのだろう。
当時企業経営に関与する人たちは、似たような解釈をしていたのだと思う。
前者は国を挙げての安売りであり、後者は民間から政府への富・所得の移転だ。
前者については労働を安くすることも含まれている。
筆者が想像していた意図からして、労働者が豊かになるなどありえない。
この構図の中での強弱は、政府>民間であり、民間の内訳で言えば、企業>労働者であるのは明らかだったからだ。
当時、本ブログでは、アベノミクスが主に生身の人間の購買力を奪うだろうと予想し続けた。
(そして、金融抑圧のマイナスをリスク資産投資によるリスクプレミアムで補うことを推奨した。)
これこそ、今さかんに問題視されている実質賃金の低下・伸び悩みだった。
筆者の解釈はおそらく大きく間違ったものではなかったと思う。
その意味で、政府や経営者など強い側の人間からすれば、これまでの変化は目的が実現されつつある過程なのだと思う。
決して、彼らの目的からすれば失敗ではなく、むしろ成功だったのだ。
筆者もまた、社会や経済のシステムをある程度安定・持続させることの意義を否定するつもりはない。
よく言えば、社会や経済のシステムを安定・持続させるという目的において、アベノミクス以降の政策は成功だったのだと思う。
そして、もちろん問題もあるし、むしろ大きくなっている。
想定通り、生身の人間が貧しくなったのだ。
大問題だ。
何事もバランスが大切ということに尽きる。
アベノミクスに限らず、日本が長く続けてきた外需を取りに行こう、死守しようという政策では、生身の人間が貧しくなりがちだ。
内需は拡大せず、輸入物価は上がり、家計は購買力を奪われ、それが内需産業を傷めつける結果、政府は外需中心の政策に固執してしまう。
(ちなみに、国際収支や資本の不均衡という問題までついてくる。)
喧伝されてきたほど外需産業からのトリクルダウンは大きくない。
生身の人間を豊かにしようというのが目的ならば、明らかに失敗なのだ。
しかし、そもそも本当の目的はそこになかったように思える。
岸田政権以降を批判する人は多いが、少なくともアベノミクスよりはよくなったとも受け取れる。
アベノミクスや安倍政権がひどく間違っていたとは思わないが、安倍政権は支持を集め過ぎた。
強いモノには強固な取り巻きが形成され、仮に建設的なものであっても反論を許さないような風潮があった。
それがなくなっただけでも進歩だと思うが、皮肉なことに、それゆえに強い批判を浴びやすい状況になっている。
これでは上下左右いずれの方向にも進めないのではないか。
河野氏の著書は、建設的な議論を行うための優れたプラットフォームになるように思う。
日本は早期に現状認識と問題提起を終え、次の大仕事、弥縫策に留まらない、より具体的な制度・ルール・仕組みの提案に進むべきだろう。
 山田 泰史 横浜銀行、クレディスイスファーストボストン、みずほ証券、投資ファンド、電機メーカーを経て浜町SCI調査部所属。東京大学理学部卒、同大学院理学系研究科修了 理学修士、ミシガン大学修士課程修了 MBA、公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。
山田 泰史 横浜銀行、クレディスイスファーストボストン、みずほ証券、投資ファンド、電機メーカーを経て浜町SCI調査部所属。東京大学理学部卒、同大学院理学系研究科修了 理学修士、ミシガン大学修士課程修了 MBA、公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。