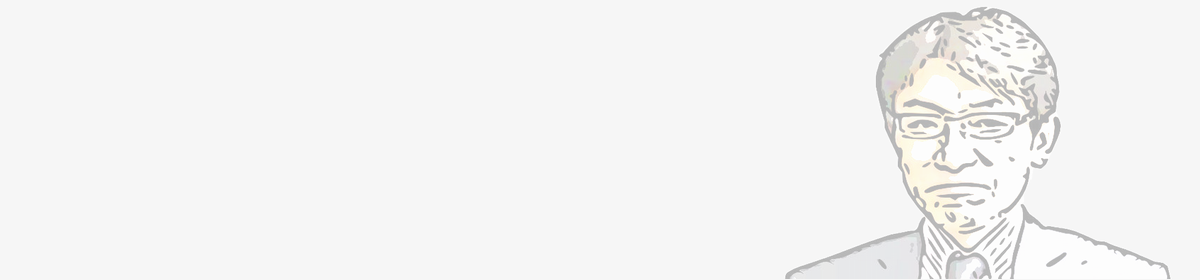河野氏の新著『日本経済の死角』に対する3つの所感の2つ目は「フリードマン=ジェンセン原則の『企業経営者の役割は、株主価値の最大化』」が問題を助長したとの指摘。
フリードマンやジェンセンの意見を否定するというよりは、この「原則」が「自らの利益が膨らむと期待した経済エリート」たちにより「『強欲資本主義』を正当化するロジック」として使われたとの指摘である。
2つ考えさせられる指摘があった。
- 「『株主至上主義』のコーポレートガバナンス改革」の問題点
- 個別企業を見ないパッシブ・ファンドが議決権行使助言会社を用いて議決権を行使することがアクティビストを助けることがある
いずれも指摘のとおりだとは思うが、これらは一般論で括るべき話ではないような気がする。
コーポレートガバナンス改革と言えば、2023年の東証の提言などが思い出されようが、これなどは東証の善意をセルサイドをはじめとする業界関係者が曲解と言っていいほど悪質に利用したものだ。
本来の趣旨は、企業価値向上に資することを探索し投資し、それでも残る資金があれば抱え込まずに投資家に還元すべきというものだったが、一部が切り取られ悪用されている。
その意味で河野氏の指摘はまったく正しいが、それがすなわち《株主価値の最大化》という方法論を否定するものでもない。
筆者の個人的な意見を言えば、経営者に権力を与えすぎるのは決してよくない。
独立役員がいようと、そんなものが十分に機能しないことはすでに実証されていると思う。
だから、経営者にプレッシャーを与えうるステークホルダーが必要だと思う。
筆者が考える候補は3者:
- 顧客: これはかなり機能しているのだろうが、難点を言えば、顧客は経営者についてはほとんど情報を持たない。
- 従業員: このステークホルダーの一部はもっとも経営者に対して知見を持ちうるが、独立役員と同様多くを期待できない。労働組合はそもそも弱体化されてしまった。
- 投資家: かつて企業が借金をしていた頃は銀行による監視がある程度は機能していた。今は企業の多くがカネ余り。残ったのは株主。
経営者についてよく《企業価値を高め、各ステークホルダーに適切なバランスで配分するのが使命》などと言われることがあるが、それは美辞麗句にすぎない。
神様でもない限り、そもそも《適切なバランス》を知ることさえほぼ不可能だ。
経営者はこれを悩み続けなければならないが、社会はそれを経営者だけに押し付けていいわけでもない。
そこで、最後に残る可能性が株主だと思う。
株主とは、損益計算書の最後の最後の当期利益から分配を受ける存在だ。
もっとも意識が帳尻に届くステークホルダーだろう。
こうした課題は、代替手段と一対で議論したいところだ。
河野氏も、株主至上主義が悪いから、株主の権利を弱めればよいと言いたいわけではないはずだ。
仮に株主の権利を弱めれば、多くの経営者は以前にも増して現金を貯め込もうとしかねない。
そもそも、アクティビストの主張の中にもまともなものも少なくない。
まして議決権行使助言会社の助言の多くは、完璧とは言わないものの、相応の理のあるものが多い。
少なくとも、持ち合いでただただ沈黙を続ける株主、ほとんど経営内容の勉強をしていない一部の一般株主、総会屋などに比べればはるかにましだ。
問題は問題として存在するのは間違いないが、私たちは内容を個別に見て、有効な代替案を議論することが重要だろう。
(次ページ: 「収奪」は意図されたものではなかったか?)