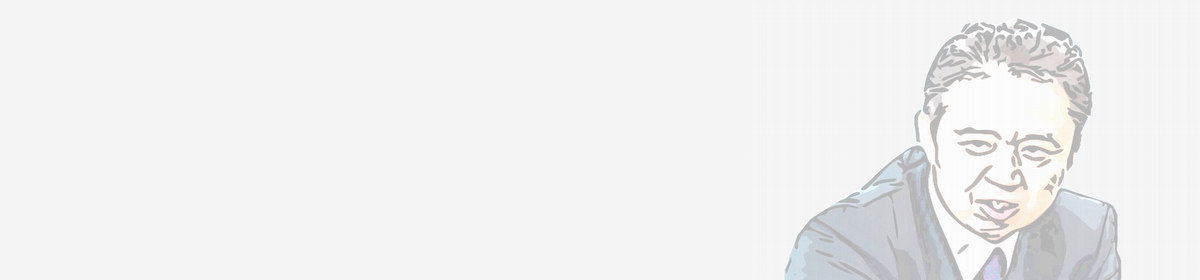ふくおかFGの佐々木融氏が、ドル相場、円相場、ドル円相場、豪ドル相場について方向性を語っている。
日本のインフレ率は3年間2%以上を維持しており、植田(日銀)総裁の言う『基調的な物価』が何を示しているのかだんだんわからなくなってきている。・・・
G7の中で英国に次いで高く・・・少し前までは一番高かった。・・・
日本はインフレが高い国になっているのに関わらず政策金利は一番低い。
佐々木氏が自社ポッドキャストで、引き続き円安基調を予想した。
金利差のほか、貿易収支・サービス収支での赤字や、通商交渉での対米直接投資の約束などを材料に挙げている。
IMM投機筋ポジションで積み上がっていた円買いが解消するにつれ円安ドル高が進んでおり、すべて解消する場合ドル円は1ドル155円付近まで上昇するとの推計を述べた。
年末については予想が難しいとしたものの、155円と話している。
日銀は先月31日までの金融政策決定会合で金融政策の据え置きを決定した。
会合後の会見で植田総裁は関税の影響を心配する一方、「基調的物価」が2%に近づいているいるとの見解を述べた。
裏を返せば、「基調的物価」がいまだ2%目標に届いていないとの考えであり、これが利上げを急がない理由の1つとされている。
日本のCPIは2022年半ば以降、総合指数が前年同月比3%前後で推移し、6月は3.3%。
(コアコアも2022年10月に2%を超え、2024年7月に一時1.9%まで低下したが、その後再上昇、6月は3.3%となっている。)
日銀が「基調的物価」と定義する数字の上昇率は2%に満たないようだが、現実の物価は3年ほど3%前後で推移していることになる。
日銀の考え方は理論的なものなのだろうが、結果、物価の番人が高インフレと円安を放置する構図になってしまっている。
佐々木氏は、ドル相場の方向性として、売られる可能性が高まっていると指摘する。
「今回の(労働統計局長解任)で、今後その労働統計局が出す数字を本当に信じていいいのかわからなくなってくる。
労働統計局は雇用統計だけでなくCPIやPPIも出している。
信用できるかわからなくなると、投資も控えたくなる。」
なお、佐々木氏は米労働市場について、過度な悲観は時期尚早とも述べている。
民間の統計では改善しているものもあり、今後幅広い指標を注視すべきと話している。
佐々木氏はさらに、短期では逆にドル高要因も存在すると話す。
「日本・EU・韓国は米国に多額を投資すると約束している。
そのフローが出て来ると・・・意外に短期的にはまだドルは支えられるのではないか。
・・・円は相変わらず今年も弱い通貨なので、ドルが弱ければドル円はさほど上がらないが・・・ドル円はそんなに下がらないのではないか。」
佐々木氏は長期で推奨してきた豪ドルについて、短期の見通しを述べている。
「豪ドルは関税のゴタゴタで売られていた方の通貨。・・・
ドル円が上昇していくなら、豪ドル円もそれなりに上昇すると予想している。」